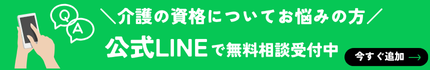- 初任者研修とは?
- > 介護の仕事の実態は?介護の仕事は離職率が高い?仕事内容ややりがいなども公開!
介護の仕事の実態は?介護の仕事は離職率が高い?仕事内容ややりがいなども公開!
介護の仕事は「離職率が高い」「きついわりに給料が安い」などのイメージを持たれがちですが、実際はどうなのでしょうか?
ここでは、介護の仕事内容や実際のスケジュール、介護職の良いところ・悪いところから、介護の仕事の実態を大公開します。
介護の仕事って具体的に何をするの?

一口に「介護」といっても、その内容は利用者の身体状況や施設の種類の違いによって多岐にわたります。
多くの人が思い浮かべる食事や排泄の介助はもちろん、歩けない利用者の代わりに掃除や買い物をするのも介護ですし、利用者やその家族の相談に乗るメンタルケアも介護の仕事のひとつです。
ここでは、代表的な介護の仕事の内容について、詳しく解説していきます。
食事介助
利用者のために食事を準備するところから始まります。
利用者によっては噛んだり飲み込んだりが難しい方もおりますので、刻み食やとろみ食などひとりひとりに合わせた形状で食事を作り提供します。
食事中は、利用者が楽しんで食事ができるよう、声掛けや食事の取り分けなど、コミュニケーションを取りながら介助します。
食後の服薬の介助は特に注意が必要です。容量以上に飲んでしまったり、ほかの人の薬を取り違えたりしないよう、介護者がしっかりとサポートしてあげる必要があります。
食前・食後は、うがいや歯磨きを促し、口内を清潔に保つことも大切です。
入浴介助
利用者の衣服の着脱や、洗身・洗髪など、入浴の介助をします。
お風呂場は滑りやすい為、手すりやリフトなどを活用して安全に注意する必要があります。また、温度の変化から体調を崩す利用者もいるため、事前の健康チェックや湯音の管理など健康面への気配りも大切です。
入浴介助は介護の中でも体力のいる仕事ですが、利用者の気持ちよさそうな顔が見られるのでやりがいを感じると話す介護士も多い仕事です。
排泄介助
毎日決まった時間に排泄を促しますが、回数は利用者それぞれで異なるので、常に気をつけておかなければなりません。
排泄を他人にゆだねること自体がストレスになりやすいため、信頼関係が重要になります。また、精神的・身体的ストレスを最小限にするため、なるべく自立して排泄を行えるように手助けを行います。
利用者によってはオムツの交換やポータブルトイレの洗浄なども行います。
移乗・移動介助
ベッドから車いすへの移動や、歩く、座るといった動作を安全に行えるように介助します。
また、つえや車いすが安全に使用できる状態かという器具の点検も行います。歩行が困難な方にとって、安全に移動できるかどうかは、寝たきりになってしまうのを防ぐためにも大変重要なことになります。
レクリエーション
工作をしたり、カラオケや体操をしたりと、その場のみんなが楽しめる内容レベルを考えてレクリエーションを行うのがポイントです。
レクリエーションには、身体機能の回復・維持だけでなく、生きがいや仲間づくりという目的もあります。自分も利用者と一緒になって楽しむことで信頼関係が生まれ、その後の仕事もやりやすくなるでしょう。
介護の仕事、一日の流れを公開
続いては、実際の勤務がイメージしやすいように、介護の仕事のタイムスケジュールを見ていきましょう。
介護の仕事には、働く場所によって、利用者が施設で生活する「入所型」、利用者がその都度施設に通う「通所型」、介護士が利用者の家に訪問する「訪問型」とあり、サービスに合わせてタイムスケジュールも変わってきます。
ここでは「入所型」にスポットを当てて紹介していきます。「入所型」は24時間体制で介護を行いますので、早番、日勤、夜勤など3〜4交代制のシフトでの勤務となります。今回は日勤、夜勤のタイムスケジュールを見ていきましょう。
日勤の場合
8:30 出勤・朝礼
朝礼。夜勤の職員からの引継ぎ。
夜間の状況などについて、夜勤者から細かく情報共有します。
また、今日の動きや特別時効などについても確認します。
9:00 排泄介助
トイレへの誘導やオムツ交換など。
10:00 入浴介助
自分ではお風呂に入れない利用者の洗髪、洗身の介助など。
11:30 昼食、服薬、口腔ケア
お食事を準備し、食事の介助をします。
利用者さんによって調理の仕方(細かくしたり、ペースト状にしたりなど)や、食後の薬の種類も違うので、ひとりひとりにあった介助が必要です。
食後の口腔ケアも重要です。
13:00 休憩
14:00 リハビリ、レクリエーションなど
散歩に行ったりレクリエーションを楽しんだりと、利用者がゆったりと過ごしていることが多い時間です。
排泄や入浴の必要がある利用者さんは、この時間にも対応します。
15:00 おやつ
16:00 ミーティング
重要事項の共有や施設内の問題などについてミーティングをします。
知識・スキル向上のための勉強会などをすることもあります。
16:30 日報・カルテ記入 / 引き継ぎ
食事の量や排泄の状態などをカルテに記入します。
出勤してきた夜間の職員に引継ぎをします。
17:00 退勤
夜勤の場合
16:30 出勤・申し送り
日勤の職員から引継ぎを受けます。
その日の流れ、重要事項などを確認します。
17:00 夕食の準備
18:00 夕食、服薬、口腔ケア
夕食を準備し、食事の介助をします。
食後の口腔ケアも行います。
19:30 就寝介助
ベッドへの誘導や移乗、着替えや歯磨き、排泄介助を行います。
就寝前の服薬がある利用者へ服薬の介助も行います。
20:30 消灯
21:00 随時コール対応・巡回開始
ここから1時間に1回、異常がないか巡回をします。
また、利用者からのコールに応じて体位変換や排泄介助も行います。
22:00 事務的作業
介護記録や物品の補充などを行います。
00:00〜 交代で休憩
05:00 排泄介助
一斉に排泄介助を行います。
06:00 夜間帯の記録
日勤の職員へ引き継ぐ事項や夜間の利用者の様子などを記録します。
07:00 起床介助・バイタルチェック
検温や体調確認を行います。
終わったら利用者さんを朝食へ案内します。
08:00 朝食、服薬、口腔ケア
08:30 日勤へ申し送り
出勤してきた日勤の職員へ引継ぎをします。
09:00 退勤
介護の仕事は離職率が高いって本当?

介護の離職率、実はそんなに高くない。
「介護労働実態調査」によると、介護の離職率は16.7%であり、約5〜6人に1人が離職していることが分かります。これは他の職種と比較しても平均値な数値であり、極めて高いというわけではありません。たしかに、2010年くらいまでは他業種と比べると離職率が高かったのは事実ですが、この10年で職場環境も改善され、離職率も平均並みに低くなったのです。
また、離職した人の約7割が、介護の仕事は好きだが「職場の人間関係」や「給与の待遇」などを理由に辞めています。そして、離職者の約半数が「やりがいがある」「自分に合っているから」などの理由で復職しているのです。
3Kなどと呼ばれ、一般的に「体力的・精神的にきつい職場」と思われがちな介護の仕事ですが、現場の職員の多くは仕事内容に満足しており、決して離職率は高くない仕事だといえるでしょう。
離職の理由を解説します。
それでは次に、具体的な離職の理由を見ていきましょう。
●職場の人間関係
最も多い理由としては「職場の人間関係」があげられます。
介護の仕事は様々な職種が協力し合って働く必要があります。また、作業量も多く、一人では体力的に難しい仕事などは他者と協力して進めていかなければ成り立ちません。人間関係は介護の職場において最も重要な要素の一つなのです。
しかし、介護の仕事は多忙でなかなかスタッフ間でゆっくりとコミュニケーションをとる時間を作ることができません。また、入れ替わりも激しくさまざまな人が出入りするため、人間関係が複雑化することもあり、それが原因で辞めてしまう人も少なくありません。
長く続けている方は同じ部署にとどまることが多く、独自のルールなどができていて後から入ってきた人がなじみにくいという声も聴きます。その結果、情報共有や引継ぎがうまくいかないという問題に発展しているようです。
●給与が安い
次によく聞く理由が「給与が安い」というものです。
介護の仕事はきついのに給料が安い、というイメージを持たれています。しかしそれは、介護の仕事を未経験や無資格から始める方が多いためです。
確かに未経験、無資格から始めた場合、他業種よりも給与が低いことがよくあります。しかし、資格を取得したり、経験年数が増してキャリアアップしていけば、それにともなって給料も確実にアップしていけるのが介護の仕事なのです。仮に無資格で始めた方が、10年たって介護福祉士の資格を取った場合、最初と比べて月収が10万円以上アップするケースもあります。
こちらのページで介護関連の資格をまとめていますので、資格取得に興味がある方は確認してみてください。
>> 介護資格の種類と職業
現在は国の施策として介護職の待遇改善に取り組んでおり、給与相場も年々上がってきています。資格取得やキャリアアップなど、長い目で見れば給与の面はそんなに心配しなくてもよさそうです。
●不規則な職場環境
入所型の施設では24時間体制で運営しているため、早番や夜勤などのシフトも入らなくてはならず、生活リズムが整いにくいことを理由に辞めてしまう方もいます。また、そういった施設では年末年始やゴールデンウィークなど、世間では長期休暇のタイミングでも休むわけにはいかず、慢性的な人手不足から別の日程での長期休暇も取りずらいのが現状です。
そういった面で抵抗のある方は、通所型や訪問型など、24時間体制ではなく比較的シフトの融通が利く業態で働くことを検討してみるといいかもしれません。訪問型の業態の中には「4時間から」など、短時間で働けるところもあります。
この他にも「ベッドから車いすへの移乗介助で自分の腰を痛めた」などの体力面や、「排泄介助やおむつ交換などに抵抗を感じる」などの精神的な理由から離職という人もいるようです。
介護の仕事のメリットややりがいをご紹介します
ライフスタイルに合わせて働ける
先ほど「不規則な職場環境」を理由にやめてしまう方がいると紹介しましたが、職場によっては「日勤だけ」や「夜勤だけで月10日ほど働いて残りはプライベートな時間に充てる」などの柔軟な働き方を認めている職場もあります。
また、パートタイムや派遣であれば、収入面は少なくなりますが、時短勤務や土日休みなど自分のライフスタイルに合わせて働くことができます。
働き方を工夫すれば、介護の仕事は多様な働き方を選ぶことができるのです。
就職、転職、復職がしやすい
日本は高齢化が進んでおり、これからますます介護の仕事の需要は増えることでしょう。そのため、採用されやすく、その後も景気に左右されることなく安定して働くことができます。
また、介護の資格やスキルは全国で使えますので、もし引っ越しや出産・育児などで一度仕事を辞めたとしても、すぐに就職先を探すことができます。
性別・年齢関係なくキャリアアップしやすい
介護の仕事は性別や年齢に関係なく活躍できます。実際に介護の現場で働く人の年齢層は幅広く、20代から60代くらいまで、健康であれば誰でも働くことができます。
また、キャリアアップの道筋がはっきりしているというのも介護の仕事の魅力の一つです。
はじめは無資格、未経験から入ってくる方が多いのですが、経験を積み資格を取得していくことで着実にキャリアアップを図ることができます。以前は多様化していた資格も現在はまとめられ、初任者研修、実務者研修を経て、最終的には介護福祉士の資格を取ることを目標にされている方が多い印象です。
監修者について

藤井 寿和 Hisakazu Fujii
静岡県西伊豆生まれ。
●合同会社福祉クリエーションジャパン 代表
●介護施設 現場支援コンサルタント
●一般社団法人 日本アクティブコミュニティ協会 公認講師
●介護情報誌「TOWN介護Tokyo」 編集長
●NPO 16歳の仕事塾 社会人講師
●株式会社 是眞 編集長
【保有資格】
●介護福祉士
●ホームヘルパー1級・2級
●レクリエーション介護士1級・2級
●社会福祉主事任用資格
●福祉用具専門相談員
●介護予防運動指導員
●音楽健康福祉士
●音楽レクリエーション指導士3級
●防火管理者
●大型自動車1種免許
お問い合わせはお問い合わせメールまでお願い致します。
※メールにてお問い合わせいただく際は、PCからのメールを受信できるように設定をご変更ください。
※スクール会場や講座については、直接スクールにお問い合わせください。
※試験情報・要綱に関しましては、最新の情報は各自治体・各主催団体の公式HPをご確認くださいませ。
※お問い合わせ内容によってはご返信までに2〜4日いただきます。
介護職員初任者研修の講座選びなら(最短)


BrushUP学びはスクールや学校、講座の総合情報サイト。
最安・最短講座や開講日程、分割払いなどをエリアごとに比較して無料でまとめて資料請求できます。
まずは近くのスクールをチェックしてみてくださいね♪
平日なら電話での請求も可能です。
\講座を比較して選ぼう!/
初任者研修の講座を資料請求(無料)- 無資格者・未経験者向けの記事
- 介護施設(老人ホーム)で働くには? 働きやすい介護施設とは?
- 認知症介護基礎研修
- 認知症介護基礎研修とは? 認知症介護基礎研修と初任者研修の違い
- 介護職員初任者研修とは
- 介護職員初任者研修とは?資格講座を徹底比較 初任者研修の学習内容・カリキュラム 試験難易度と合格率 最短1ヶ月で初任者研修資格取得 初任者研修は通信講座だけでは資格取得できない! 費用・価格を学校別で徹底比較 費用・価格だけでは決めない!介護職員初任者研修の選び方 初任者研修資格が無くても介護の求人募集はあるの? ニチイ学館の初任者研修 「ホームヘルパー2級」が「初任者研修」になって変わったことは? 実務者研修と初任者研修の違い 初任者研修は一つではない!? 介護職員初任者研修のほかにも初任者研修がある!? 生活援助従事者研修とは 入門的研修とは 30代でも介護職へ転職できる? 介護処遇改善手当とはどんな制度?
- 初任者研修に使える支援金・補助金
- 介護の資格に使える補助金・貸付金を一挙紹介! ハローワークの求職者支援制度とは? 特定一般教育訓練給付金とは? 市区町村が実施する「初任者研修助成金制度」とは? 自立支援教育訓練給付金とは?
- 条件別の記事一覧
- 条件別でスクール・講座を探す!記事一覧 【平日は忙しい方へ】初任者研修を土日だけで取得可能なスクール5選! 初任者研修を分割払いで受講できるスクール6選!注意点を徹底解説 介護職員初任者研修を夜間コースで受けるポイントは?おすすめスクール2選 初任者研修で就職サポートに強いスクールは?選び方とサポート内容を解説 実務者研修を土日で受講できるスクール4選!選び方とメリットを解説 実務者研修の分割払いに対応しているスクール5選!知っておきたい注意点 【厳選】実務者研修で就職支援を実施するスクール3選!選び方の完全ガイド
- インタビュー記事一覧
- 外国籍の方が介護士になるには?
- 初任者研修の講座を探す
- 全国 都道府県から探す 関東人気エリア 東京都内のおすすめスクール 東京都千代田区のおすすめスクール 東京都港区のおすすめスクール 東京都江戸川区のおすすめスクール 新宿のおすすめスクール 池袋のおすすめスクール 渋谷のおすすめスクール 自由が丘のおすすめスクール 練馬のおすすめスクール 錦糸町・亀戸のおすすめスクール 北千住のおすすめスクール 蒲田のおすすめスクール 吉祥寺のおすすめスクール 調布のおすすめスクール 町田のおすすめスクール 立川のおすすめスクール 八王子のおすすめスクール 国分寺のおすすめスクール 昭島・福生のおすすめスクール 千葉県のおすすめスクール 船橋のおすすめスクール 柏のおすすめスクール 松戸のおすすめスクール 神奈川県のおすすめスクール 横浜のおすすめスクール 川崎のおすすめスクール 藤沢のおすすめスクール 相模原のおすすめスクール 平塚のおすすめスクール 埼玉県のおすすめスクール 大宮のおすすめスクール 浦和のおすすめスクール 川口のおすすめスクール 春日部のおすすめスクール 越谷のおすすめスクール 川越のおすすめスクール 所沢・入間のおすすめスクール 熊谷のおすすめスクール 群馬県のおすすめスクール 高崎のおすすめスクール 前橋のおすすめスクール 栃木県のおすすめスクール 宇都宮のおすすめスクール 小山のおすすめスクール 茨城県のおすすめスクール 水戸のおすすめスクール ひたちなかのおすすめスクール 北海道・東北人気エリア 北海道のおすすめスクール 札幌のおすすめスクール 青森県のおすすめスクール 八戸のおすすめスクール 岩手県のおすすめスクール 盛岡のおすすめスクール 秋田のおすすめスクール 宮城県のおすすめスクール 仙台のおすすめスクール 山形県のおすすめスクール 福島県のおすすめスクール 甲信越・北陸人気エリア 山梨県のおすすめスクール 甲府のおすすめスクール 富山のおすすめスクール 石川県のおすすめスクール 金沢のおすすめスクール 福井県のおすすめスクール 長野県のおすすめスクール 松本のおすすめスクール 新潟県のおすすめスクール 東海人気エリア 愛知県のおすすめスクール 名古屋のおすすめスクール 豊橋のおすすめスクール 静岡県のおすすめスクール 浜松のおすすめスクール 岐阜県のおすすめスクール 三重県のおすすめスクール 津市内のおすすめスクール 四日市のおすすめスクール 近畿人気エリア 大阪府のおすすめスクール 大阪市中央区のおすすめスクール 梅田のおすすめスクール 難波(なんば)のおすすめスクール 天王寺のおすすめスクール 堺のおすすめスクール 枚方のおすすめスクール 滋賀県のおすすめスクール 京都のおすすめスクール 兵庫県のおすすめスクール 神戸のおすすめスクール 明石のおすすめスクール 奈良県のおすすめスクール 和歌山県のおすすめスクール 中国・四国人気エリア 島根県のおすすめスクール 松江のおすすめスクール 鳥取県のおすすめスクール 岡山県のおすすめスクール 広島県のおすすめスクール 山口県のおすすめスクール 香川のおすすめスクール 徳島県のおすすめスクール 高知県のおすすめスクール 愛媛県のおすすめスクール 九州人気エリア 福岡県のおすすめスクール 博多・天神のおすすめスクール 小倉・北九州のおすすめスクール 佐賀のおすすめスクール 長崎県のおすすめスクール 大分のおすすめスクール 熊本県のおすすめスクール 宮崎県のおすすめスクール 鹿児島県のおすすめスクール 沖縄県のおすすめスクール
- 介護の資格と職業
- 介護資格の種類と職業 介護福祉士とは 介護職員実務者研修とは 一番安い介護福祉士実務者研修 ケアマネジャーとは サービス提供責任者とは 福祉用具専門相談員の資格とは 同行援護従業者養成研修とは 訪問介護員(ホームヘルパー)とは 介護タクシーに必要な資格とは レクリエーション介護士とは